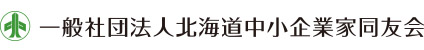第40回全道経営者〝共育〟研究集会inくしろ 感想集
2025年11月15日
記念講演と12の分科会で熱い学び
仲間が集い、地域の未来語り合う
各地から518名参加 第40回くしろ道研
全道から518名が集い、13年ぶりに釧路で開催された第40回くしろ道研。「繋ごう!次の10年へ」をスローガンに学び合った一日を、写真とアンケートで振り返ります。(カッコ内は支部)
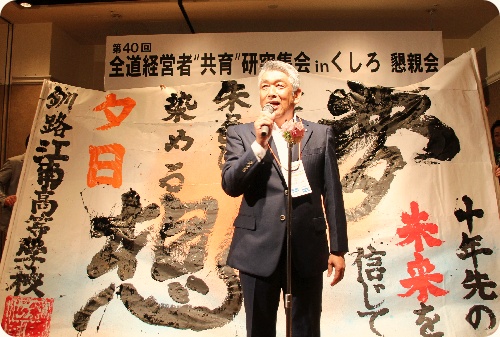
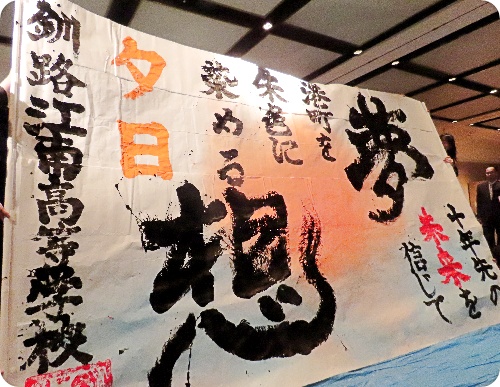

第1分科会

◆会社の基盤がしっかりしていれば社員に自由な発想で仕事ができる状況を作れる。今だけでは無く、しっかり未来を見ることを分科会、記念講演で学びました(とかち)
◆自分ごとにするために何をすべきかを考え、職員に接していこうと思います(札幌)
◆自社でも社員が自律するための教育や社風づくりは行っていますが、野尻社長の話から改善のヒントをたくさんいただきました。早速実行に移していきます(東京同友会)
第2分科会

◆人材確保のSNS化や、社員とのコミュニケーションの取り方を考えさせられました(くしろ)
◆時代の変化に対応しなければならないと感じました。法律の改定や今時の働き方など、取り組まなければならないことが山積みです(とかち)
第3分科会

◆「当たり前」をしっかり定義すること。経営方針発表会は何のため、誰のために行うかが大切。各社の「良い会社づくり」から学ぶことも多くありました。そして、最後はやっぱり「行動あるのみ」と強く思いました(東京同友会)
◆自社でも経営理念を作り、従業員との良い関係を築き、会社を続けられるよう頑張りたいです(オホーツク)
◆実践が利益につながる本質を学べて共感できる部分が多々あり、勉強になりました(しりべし・小樽)
第4分科会

◆「地域に根差した企業」を目指すにあたり、非常に学びの多い内容でした。今回学んだことや出会った人を大切にして、企業活動を行っていきたいと思います(くしろ)
◆素晴らしいお話をお伺いすることができて良かったです。特に座長の趣旨説明と最後のまとめが適確かつ簡潔でとてもわかりやすかった(函館)
地域や業種の垣根を超えた視点共有
第5分科会
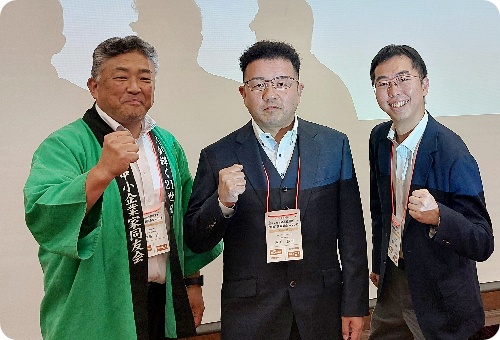
◆柔軟な発想力を持って挑戦しながら、時にはやめる判断も必要だと学びました。まずは社員が気持ちよく働けるような環境を作ることが大切とわかりました(くしろ)
◆「良い」と思ったところはすぐに実行したい!(くしろ)
第6分科会 命守るネットワークを

◆会員企業のネットワークを活かした声かけや情報共有の重要性。常に有事に備えるという意識と、仲間を思いやる気持ちが一番大事だと感じました(くしろ)
◆災害時に最も重要なことは自らの命を守ること。自分自身や家族、社員を守ることが出来て初めて、その先の自社の経営や地域のことについて考えるべきと改めて学びました(くしろ)
◆業界内で防災訓練の実施や、危機意識向上が必要。緊急時の対応を手順化し、しっかり周知していきたい(とかち)
第7分科会

◆熱い情熱と仲間がいれば、何にでも挑戦できる事がわかりました。「情熱をもって夢を語れ!お金はあとから付いて来る!」の言葉を糧にしたいと思いました(オホーツク)
◆考えても行動に移すことはなかなか難しく、継続させることは更に胆力が必要になります。藤本社長の行動力と情熱がまわりに伝わり、信頼を勝ち取ったのだと思います。簡単にはできないことで大変勉強になりました(くしろ)
第8分科会

◆自社の強みをどのように事業拡大に活かしていくかを構造的に学ぶことができ、大変有意義でした(札幌)
◆とにかく、やることが必要!(しりべし・小樽)
◆業種は違っても秘めている想いは一緒で「こだわり」を持ち前に進んでいると気付きました。最後はグループ全員で同じ気持ちになり学びの多い時間になりました(くしろ)
◆分科会、記念講演、意見交換を通して今までの自分の考え方を違う視点で見つめ直してみようと思いました(くしろ)
第9分科会

◆谷川会長の従業員に対する想いや、皆さんの意見を伺い、改めて自社の待遇を見直す機会をいただきました(とかち)
◆人を雇用し続けていく中で物心両面の幸せを企業としてどのように捉え、社員に与えていくかを考える良い機会になりました(札幌)
◆会員企業が努力をしながら従業員の幸せを考えていると改めて実感しました。気付きも多く、今後の経営に繋げていきたいと感じる分科会でした(札幌)
第10分科会

◆両社とも「事業領域」を積極的に拡大されており、大変勉強になりました。改めて自社の「事業領域」を見つめ直してみたいと思います(東京同友会)
◆両社長をはじめ、社員の皆様の準備と対応に感心・感謝・感動!自社でも経営者、幹部、社員が一丸となって更なる発展を目指していきます(函館)
第11分科会

◆設備投資に見合ったリターンを計算することの大切さや、社員を採用できる環境を作り、会社も共に成長していく。目指すべき姿はそういった経営だと感じました(三重同友会)
◆自社で酪農に関する仕事を行っているが、農場に足を運ぶ機会がなかったので、現場を知る良い分科会になりました(くしろ)
第12分科会

◆これまで他のジャパニーズウイスキーの印象が強かったが、厚岸に根付き始めた文化として大切にもっと広げていきたいと感じました(札幌)
◆実際にその土地を走り、体験できるのが移動分科会の良さ。最高でした(函館)
◆美味しいだけでなく、学びも多い分科会でした。報告者の皆さんの真面目さ、商売の精神をしっかりと感じることができました(札幌)
◆ウイスキーも牡蠣も地域の自慢として語れるものがあるのは素晴らしいことだと感じました(オホーツク)
第2分科会
求職者に選ばれるための採用戦略 企業の強みを見える化事例も

温泉宏楽園・米山佳宏専務(小樽)、満寿屋商店・杉山雅則社長(帯広)、島本鉄工・島本勇平社長(釧路)が報告しました。
各社から採用への考え方や求める人材像、働く環境づくりや社員教育、定着促進の取り組みや求人活動の具体的な実践が報告されました。さらに企業の強みを見える化した事例などもあり、求職者に届くよう「伝える」ことの重要性が明らかになりました。
グループ討論では、「社員の力を引き出し、定着を図るためには」「魅力ある企業をどうつくっていくか」などのテーマで活発に意見交換しました。
第10分科会
モノづくりの力で地域支え、挑戦し続ける

ニッコー代表取締役 佐藤 一雄氏(釧路)
人手不足加速で、ロボットリテラシーに注目。エンジニア育成のため、専門の講師による高専への講師派遣や企業向け講習会も実施しています。
研究開発のために当社のロボット施設を各社に提供するなど、進化するロボット技術で地域を支える企業を目指しています。
釧路製作所代表取締役社長 羽刕 洋氏(釧路)
変化を恐れず新分野を切り拓き、地域の雇用を守ろうと産学官連携を活かし宇宙事業へ挑戦しています。
企業の役割は、夢と希望を与えるビジョンを掲げ、社員の生活を守り、地域へ貢献することです。こうした戦略をもとに、未来を見据えて100年企業を目指しています。