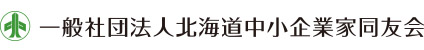【1世紀企業 89】丸い遠藤商店(小樽市)
2025年10月15日

小樽のまちと共に120年
信頼つなぐ米と酒専門店

遠藤商店は1906(明治39)年、越後(新潟)出身の初代・遠藤小平治氏がわらじや糸などを扱う小間物屋として、小樽市豊川町にて創業しました。当時の小樽は港と鉄道の結節点として急速に発展しており、地域の生活に欠かせない存在として親しまれていました。
昭和に入ると二代目・遠藤小平治(襲名)を中心に次第に米穀専門店へと姿を変えていきました。3代目・遠藤幸吉氏の時代には、「町の米屋・酒屋」として地域に根差した営業を続け、着実に信頼を築いていきます。ところが83(昭和58)年、幸吉氏が交通事故により急逝。まだ大学四年生だった次男・遠藤友紀雄氏が急きょ家業を受け継ぐこととなりました。
若き4代目にとって、経営の現場も顧客の視線も厳しく、日々が試練の連続でした。当初は「若さ」による不安の目も多く、経営者としての信頼を得るまでには時間を要しました。93(平成5)年には記録的な冷害が発生。国産米が深刻な品不足となり、国の施策によりやむを得ずタイ米を緊急輸入して販売することになりましたが、国産米を求める消費者の支持は得られず、赤字が続きました。さらに95(平成7)年には食糧法が改正され、米の流通が自由化。農協を通さずに誰でも販売できるようになったことや、大手スーパーが次々と進出し、個人商店は苦境に立たされました。
この危機を転機と捉えた友紀雄氏は、「量より質」への方向転換を決意。後志地方の農家と直接契約を結び、減農薬・減化学肥料で育てられた安心・安全なお米の取り扱いを開始しました。玄米の量り売りや、好みに応じた店頭での精米、生産者の顔が見えるPOP掲示など、「顔が見える売り方」にこだわることで、買い手との信頼を深めていきました。
また、97(平成9)年には酒類販売の自由化に合わせてワインの取り扱いも本格化。道内外のワイナリーを訪ねて選び抜いた銘柄を揃え、現在は約8000本を常備。ワインはこだわりのお米とともに全国の顧客にも販売しています。
こうした地道な取り組みが評価され、小樽市内の飲食店はもとより、東京の高級ホテルや料亭へも米を卸売するまでに成長を遂げました。
2022(令和4)年には、四代目・友紀雄氏の長男である慎一良氏が、食品卸売会社での勤務経験を経て入社。五代目候補として、業務に必要な資格の取得を目指しながら、知識と経験を積み重ねています。「入社からわずか3年の間にも、コロナ禍やお米の供給不足といったさまざまな課題に直面しました。先人たちの想いを受け継ぎながら、今の時代に求められるかたちで、遠藤商店を守り続けていきたい」と語っています。
創業から120年。遠藤商店は、初代・小平治氏から慎一良氏まで、家族の思いと共にのれんを守り続けてきました。「質にこだわったものを届ける」という信念のもと、小樽のまちと共に歩み続けています。