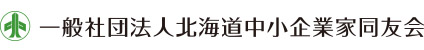【講演録】北海道酪農をめぐる情勢~トランプ関税、飼料価格、気候変動、消費動向~/農林中金総合研究所 リサーチ&ソリューション第2部主席研究員 小田 志保 氏
2025年09月15日

◆トランプ関税の影響
トランプ関税の日米合意では、飼料用の米国産トウモロコシの輸入拡大をうたっていますが、トウモロコシ輸入量を国別にみると、2022~23年度に5割近くまでシェアを拡大していたブラジル産が24年度には2割まで減少し、米国産は8割まで戻っています。ブラジル産と米国産の国際価格を比較すると、24年後半ではブラジル産の方が若干高値であったことが理由とも推測され、さらに、米国産をこれ以上増やしても国内の配合飼料価格への影響は大きくないと思われます。
◆日本の酪農
2010年代に乳用牛頭数(2歳以上)はマイナス12・5%となる一方、乳用牛向けの配合・混合飼料の生産量はマイナス3・2%。つまり、規模拡大に伴い、濃厚飼料の多給がうかがえます。同時に、2000年以降は、配合飼料価格の上昇幅が乳価のそれより大きく、酪農経営の苦境が改めて理解されます。
◆資材高騰で離農
指定団体への受託農家戸数を期間別(2010―15年、15―20年、20―24年)にみると、三重県や山陰のように、過去の酪農危機でも離農が進み、北海道以上に大規模層への集約が進む地域もあります。注意したいのは大規模層は後継者を確保しながらも、牛舎等の更新が遅れている恐れがある点です。現在の酪農危機の影響が長期化することを避けるため、行政や関連産業の支援が求められます。
乳用牛の飼育頭数は24年2月には1・19万頭となり、平均飼養頭数は110・3頭、経産牛頭は数平均69頭。10年以降は1―49頭数の経営体数は半減し、50―99頭層で1700経営も減少しました。一方北海道は大規模経営の割合が高く、特に500頭以上で上昇。10年代には100頭以上の層が17%から25%へと増加しました。
◆家計の消費動向
物価高騰で牛乳乳製品の買い控えも進んでいます。2000年以降でみると、カルシウム摂取量は厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」における推奨量を満たせないまま減少傾向です。6歳以下の層では00年~23年にかけてカルシウム摂取量が減少。00年以降では60歳以上層で乳類摂取量は増加がみられるものの未成年では減少しています。牛乳摂取量は若年層ほど多く、近年はチーズや発酵乳の摂取量は高齢者層で需要が増加しています。
また、団塊世代は在宅介護が中心で、高齢になっても都市に住み続ける傾向にあります。そうした中、都市部の高齢者向け市場で重要となるのが宅配事業です。明治の宅配事業では、契約者の8割が60代以上で、森永乳業は昨年3月に宅配事業を「健幸サポート便」に刷新しました。また、温暖化もあり、乳業大手は北海道内に工場を集中させていますが、国内人口減もあり今後は輸出拡大に力を入れていくでしょう。(8月5日、釧根農業経営部会8月オープン例会)
| おだ・しほ=2005年10月~06年11月ドイツのフンボルト大学資源経済学研究科付属協同組合研究室在籍、08年3月北海道大学農学研究院協同組合学教室博士課程修了。同年4月に、農林中金総合研究所入社。 |